
実は日本の多くの高校生が、危機感を感じています。
| 調査 | 日本の高校生の回答例 | 読み解き |
|---|---|---|
| 日本財団「18歳意識調査 6か国比較」(2024) | 「自分の国は良くなる」と答えたのは 15.3 %(中国85 %、インド78 %) | 将来像を“良くも悪くも変わらない”と見る“静観”姿勢が半数超え → 社会を動かす当事者意識が低い ( note.com ) |
| ソニー生命「中高生が思い描く将来」(2024) | **71 %**が「10年後の日本が不安」なのに、自分自身については **57 %**が「明るい」 | “社会はヤバいけど自分は何とかなる”という“他人事”バイアスが強い ( prtimes.jp ) |
要因
“危機感ゼロ”ではなく「不安はあるのに行動につながらない」――これが実態。
背景には「低自己肯定感 × 低社会肯定感 × 高リスク回避」という日本特有の三重苦があります。
また、「一見なんとかなりそうな」状況があります。
| 要因 | どう働く? | 補足ワード |
|---|---|---|
| 1. 人口減で“椅子”が余る | 少子化で大学定員に対する競争がゆるみ“とりあえず進学”で何とかなる感覚 | 「Fラン」 |
| 2. 安全ネットの厚さ | 親世代はバブル遺産&実家リソース。失敗しても食えなくなるリアル感が薄い(でも今の高校生は無理) | 実家暮らし・親の扶養 |
| 3. 教育が“正解依存”型 | 受験勉強=模範解答探し。未知を掘るより正解を当てるマインド | 知識偏重・詰め込み教育 |
| 4. 同調圧力 | “浮く=リスク”のいじめ文化。挑戦より無難さ。 | 協調性偏愛 |
| 5. ロールモデルの乏しさ | 地方ほど多様な職業人と接触しにくい。成功像が「公務員」「安定企業」 | 情弱 |
| 6. メディアの“縮小再生産” | 国内ニュース中心/英語バリアで海外ベンチマークとギャップ把握しづらい | 日本礼賛 |
| 7. 漠然不安→学習性無力感 | 「どうせ変わらない」と感じる割合が若者層で最も高い | 無力感 ( note.com ) |
この空気から、日本の高校生は抜け出せずにいます。
座談会
舞台:放課後のカフェ。テーブルにはノートPCと参考書が広がっている。

(肩にリュックを下ろしながら)
ねぇモデル姉さん、最近「背伸びせず身の丈に合った大学でいいかな」って思いはじめたんだ。受験失敗したら恥ずかしいし、奨学金の返済も怖いし…。
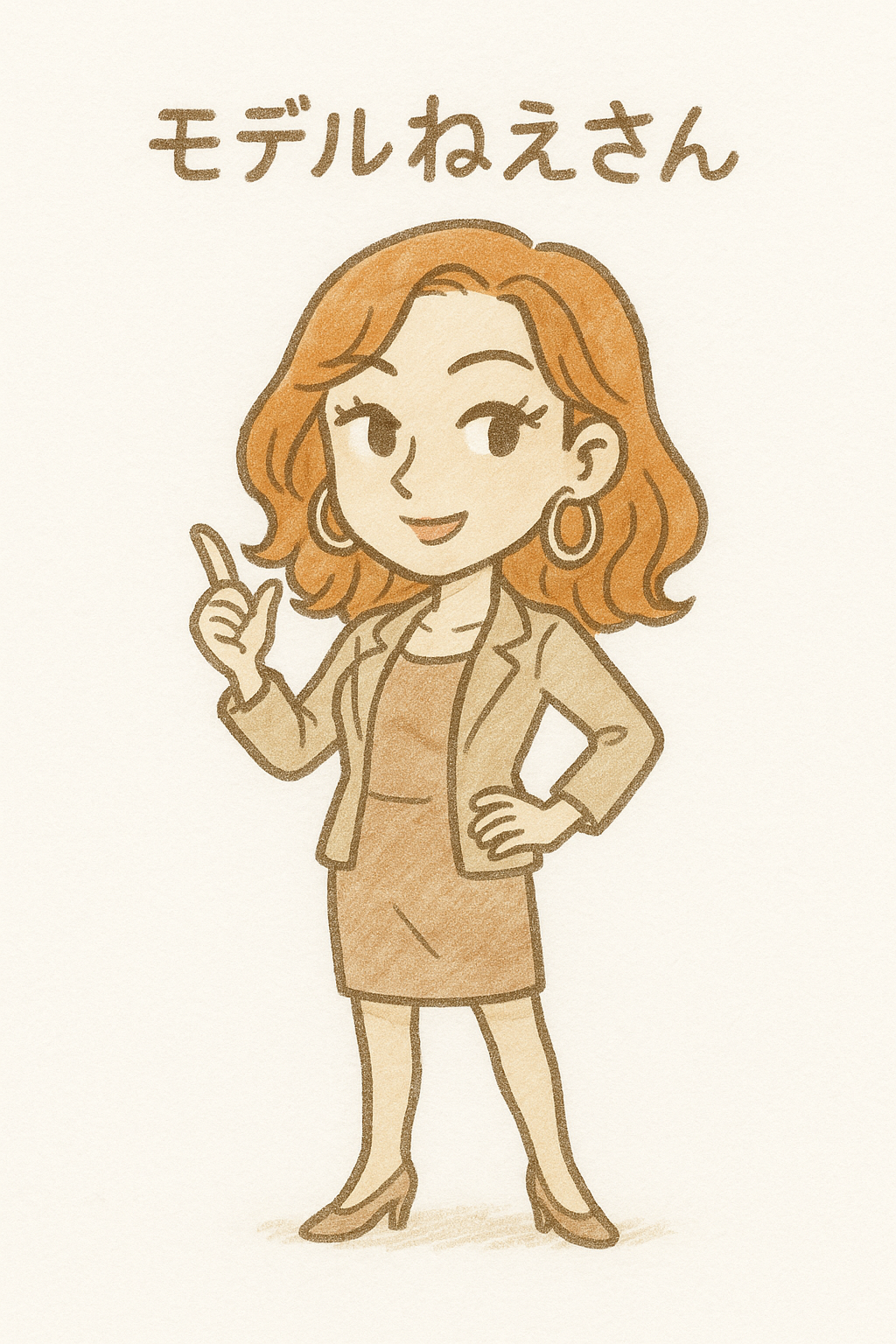
(コーヒーを一口)
その気持ち、分かるわ。でも“高望みをやめる”って、実はリスクヘッジにならないことが多いのよ。

(目を丸くする)
え、どうして? 堅実に行ったほうが安全じゃないの?
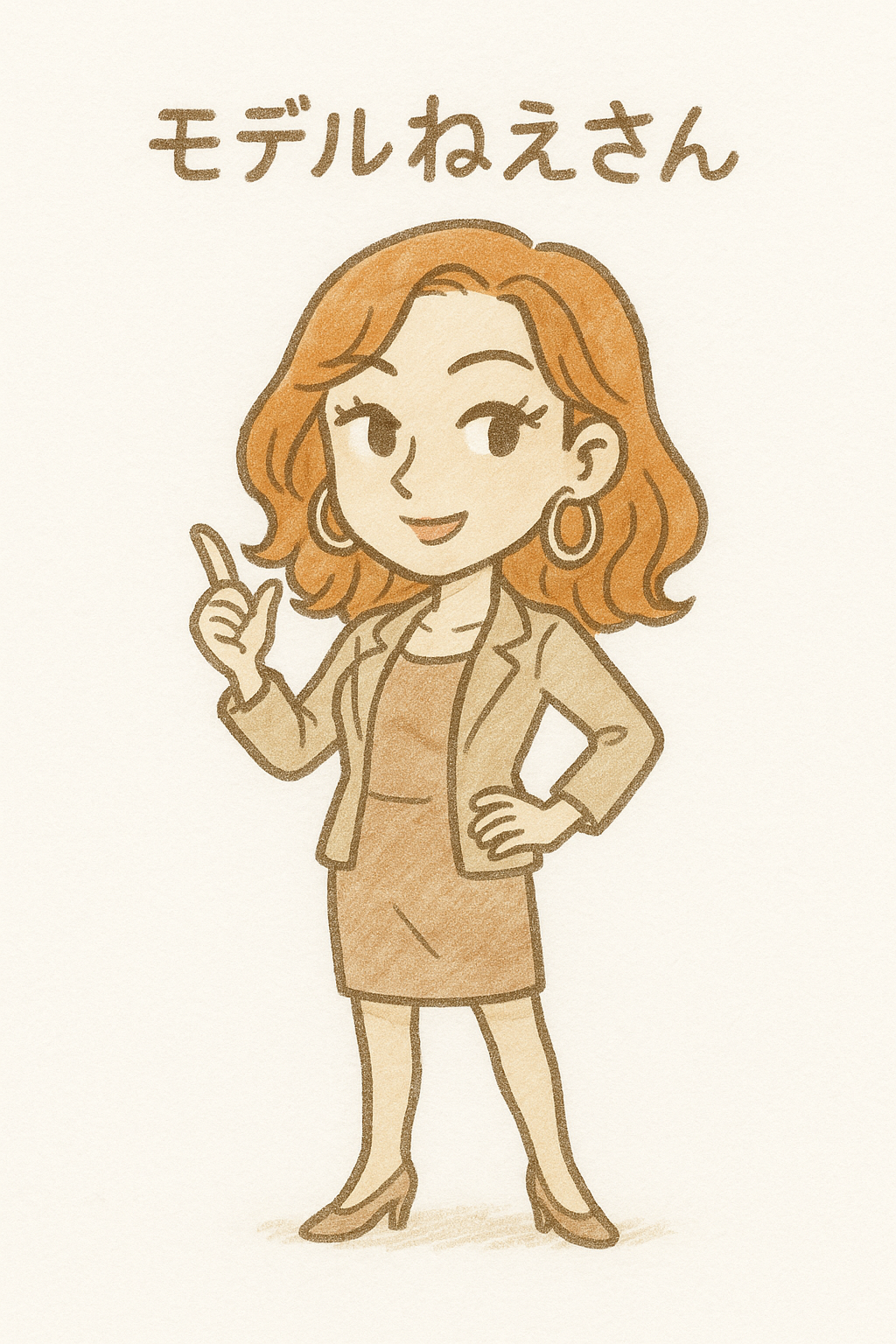
目標を下げれば短期的な“恥”や“失敗”は減るけど、
将来の選択肢が狭まる
自己効力感が育たない
という長期コストが潜在的に増えるの。しかも自分では気づきにくいからタチが悪いわ。

選択肢が狭まるって、具体的には?
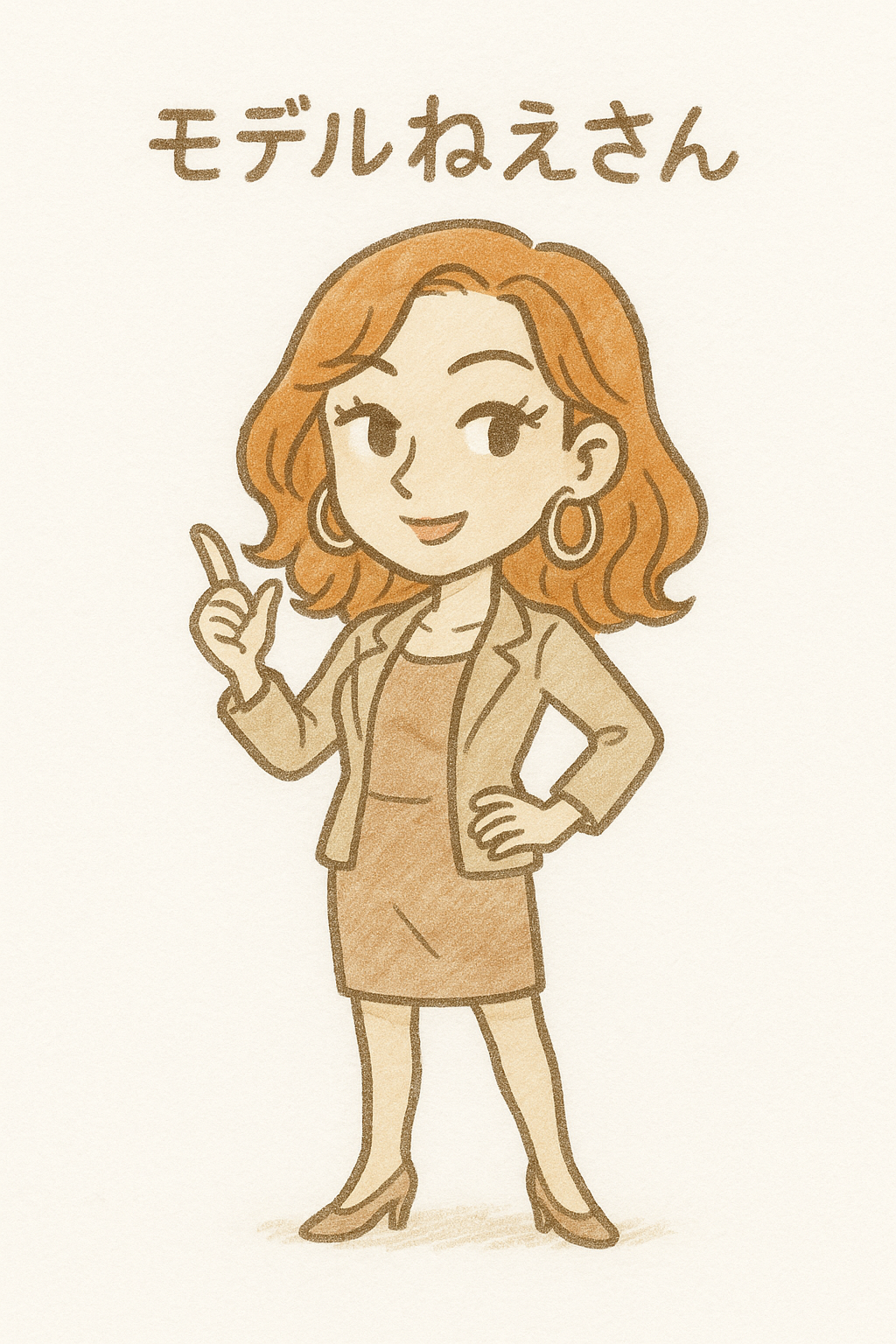
たとえば偏差値55の大学に入れば50の企業は狙えるけど、65の企業は最初から“門前払い”——そんな感じで“射程距離”が固定化されるのよ。後で上げるのは大変。

(うーんと悩む表情)
でも背伸びしすぎて全部落ちたら…?
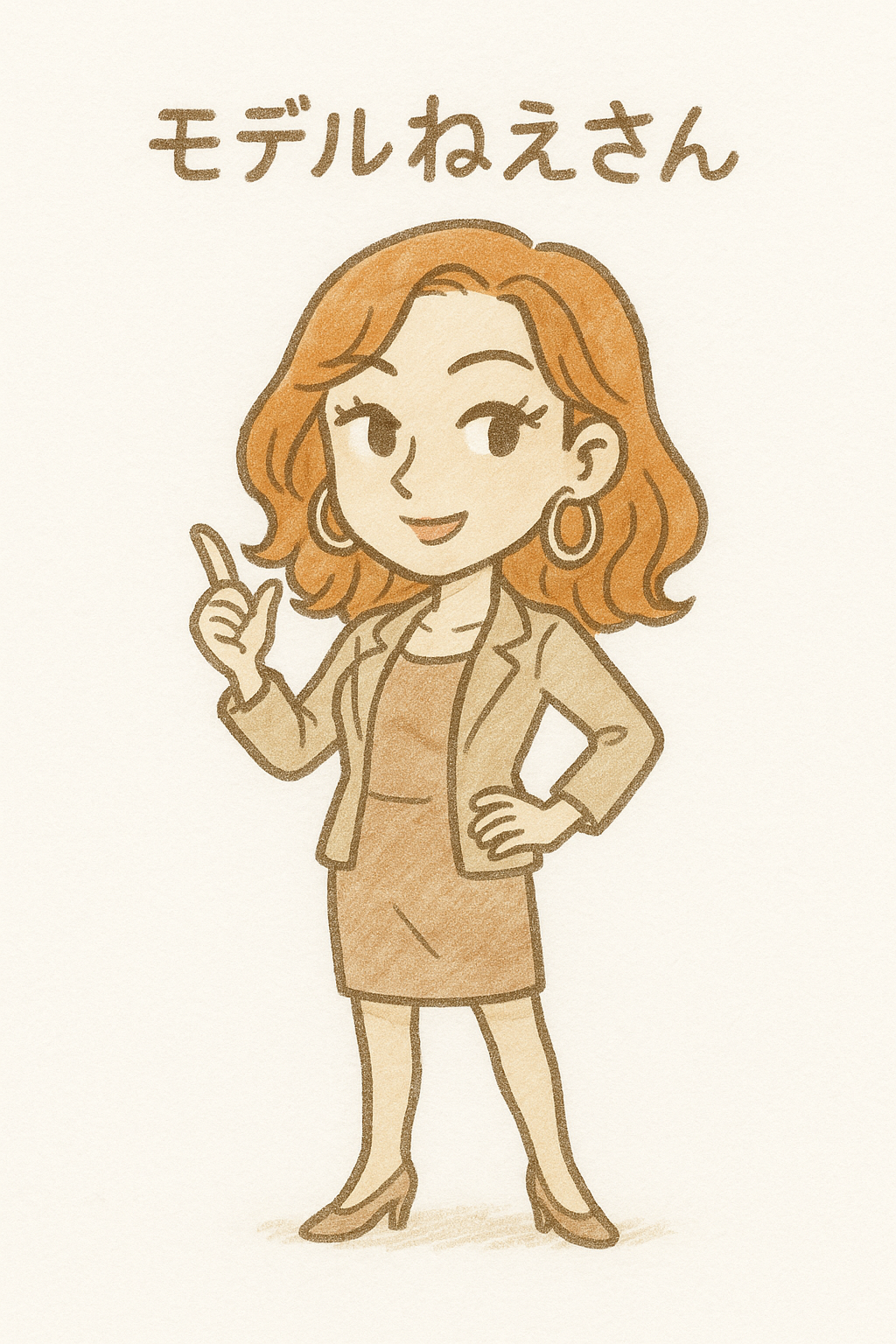
(指で 1 を作って) だからこそ“ハイリスク・ローコスト”戦略。
出願は安全校+挑戦校のポートフォリオにする。
勉強はスプリント――2週間ごとに到達度を測ってチューニング。
模試を“予行演習”じゃなく“実験”と捉えてPDCA。

(メモを取りながら)
なるほど…挑戦を設計する、ってことか。
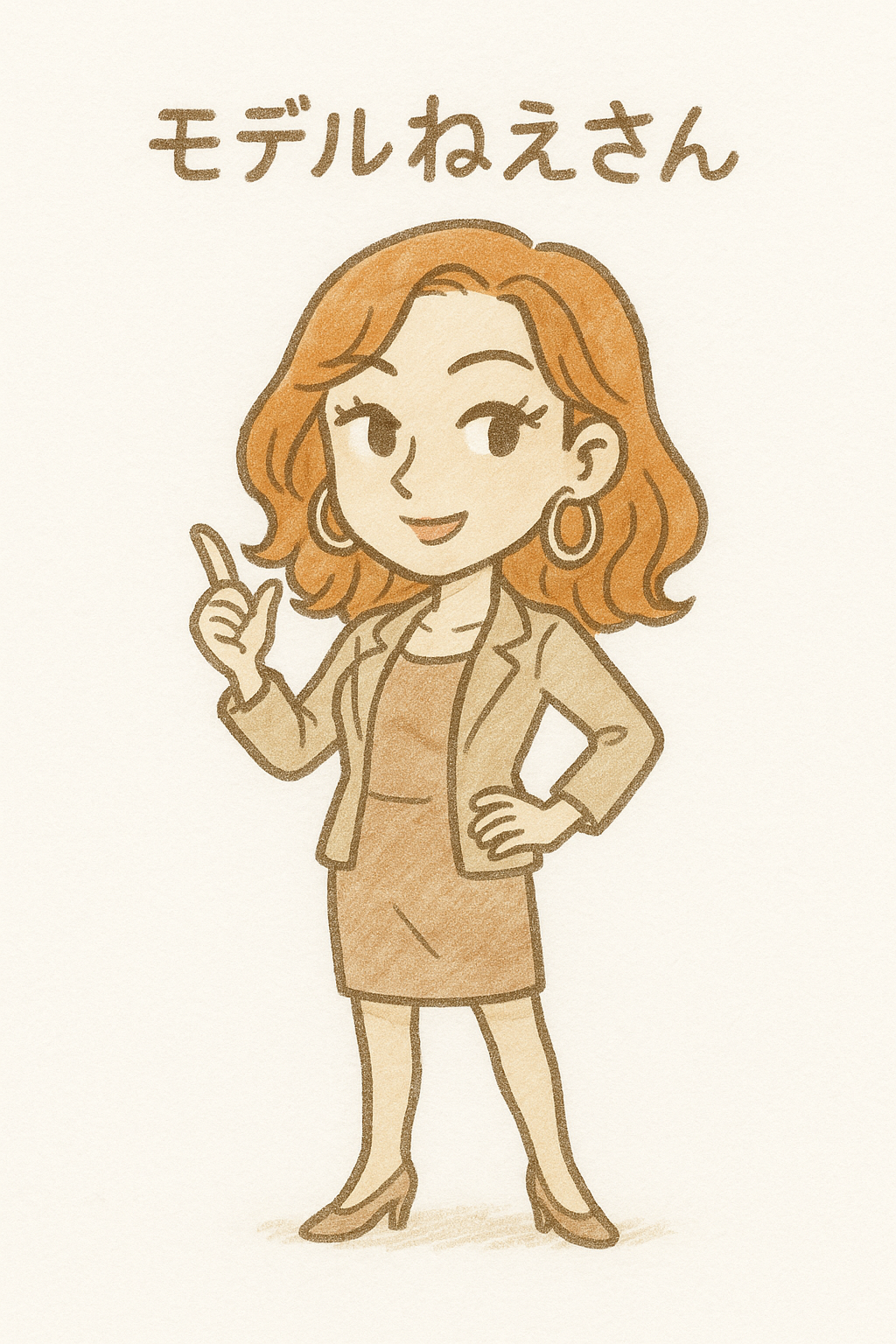
(にっこり)
そう。“高望みしない”んじゃなく“望みを具体的なタスクに分解”するの。
失敗しても「どこがダメだったか」が見えるから、次に活かせる。
—それが私の決めゼリフ、「挑戦は分割すれば怖くない」よ。

(顔を上げて笑顔)
うん、なんだか行けそうな気がしてきた!ありがとう、モデル姉さん!
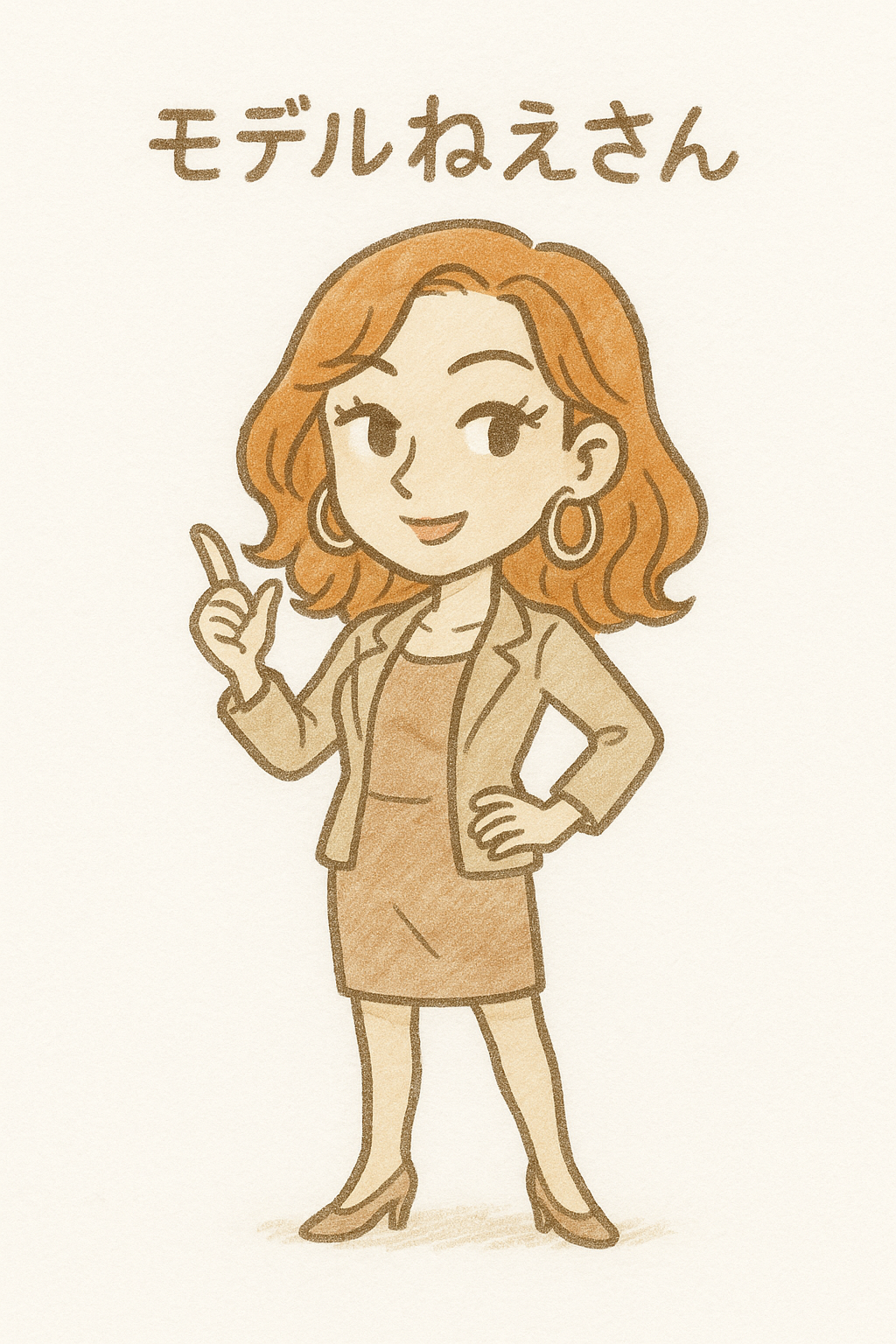
読者のみんな。無理だと決めつけなければ、年収3000万円も夢じゃないわ。
今だからこそ、高望み、Tryしてみな!
今だからこそ、高望み、Tryしてみな!