最近、大学選びをする高校生の間でよく耳にする「Fラン大学」という言葉。これは、一般的に「Fランク大学」とも呼ばれ、偏差値が低めの大学を指します。
この記事では「Fラン大学」について深掘りし、理解を深める手助けをします。
Fラン大学の定義
- 偏差値の視点: Fラン大学は、通常、偏差値が40~35以下の大学を指すことが多いです。これは国公立大学や有名私立大学と比較してかなり低い基準です。
- 入試の簡易性: 一般的には入試の難易度が低く、受験生にとって入りやすい大学として知られています。
Fラン大学はいくつあるのか?
| 区分 | 大学数 | 出典 | メモ |
|---|---|---|---|
| 日本の大学総数(2024年度時点) | 796 校 | ( eic.obunsha.co.jp ) | 国立86、公立93、私立+私立専門職617 |
| 「全学部が偏差値35未満(=真のBF)」のFラン | 73 校 | ( f-ran.com ) | “全学部BF” という最も厳格な定義 |
| 上記 Fラン を除いた大学 | 約 723 校 | 計算 796−73 | 偏差値35超えの学部を持つ大学が対象 |
| 学部の一部でも偏差値35未満なら Fランに含める場合 | 500 校超 | ( f-ran.com ) | 大学の 6 割超が Fランという試算 |
つまり、73。大学を偏差値で見るなら、下位9.2%がFランに該当します。
人工比較
9.2%という数字は、多すぎます。なぜなら、偏差値35以下は理論上 “下位 約6.7%"(おおむね 15人に1人 のイメージ)のことであり、人口より多い数が存在するからです。
つまり、定員割れしています。
2024年度は私立大の 59.2%(354校)が入学定員を充足できていませんでした。
Fラン(全学部BF)を厳格定義した 73校は大学全体の約9% に過ぎませんが、定員が小さく地方に偏るため充足率が特に低くなりがちです。
「偏差値35以下層(理論値6.7%)」より Fランに割り当てられた“席”の方が多い──という需給ミスマッチが、実際の定員割れにつながっています。
Fラン大学の実情
- 質のばらつき: Fラン大学にも良いプログラムや熱心な教授がいる大学がある一方で、教育の質が低いとされる大学も存在します。すべてが同じレベルではありません。
- 就職活動の影響: Fラン大学を卒業した場合、就職活動での苦労があることも事実です。企業の評価や求人の質が大学の偏差値に影響を受けることが多いためです。
全学部が偏差値35以下かどうかで、大きく変わります。
“学部のどこかがBF”を含む広義Fランは500校超もありますが、ここには看護・保育など地域需要が強い学部も混じり、学部単位で満席のケースもあるのです。
当然そのような大学のそのような学部であれば、教育の質も就職活動も強いです。
つまり、そこに進学しようとすると、どうしても目標偏差値を上げることになります。
Fラン大学のメリット
- 入学のチャンス: 偏差値の低い大学は、志望校の壁が高いと感じる受験生にとって、大学進学の新しい道を提供します。
- 行動の自由度: 小規模な大学では、教授と近い距離で学びやすく、個別指導を受けることができる場合があります。
まとめ
可能性は、どの大学にも隠れていますが、可能性が顕在していれば、受験生からの人気は高まり、結果的には偏差値は上がります。
そのため、基本的には偏差値を上げるという結論になります。
座談会

Fラン大学の話を聞いて、少し不安になっただっちゃ。でも、地元には質の高い教育を提供している大学もあるんだから、考え方次第で可能性が広がると思うな〜。

やばっ!それ、めっちゃ大事な視点だね。入試の難易度が低いからって、全てがダメってわけじゃないもんね。実際、行きたい大学でモチベーション上げて学ぶことができれば、いい経験ができそう!
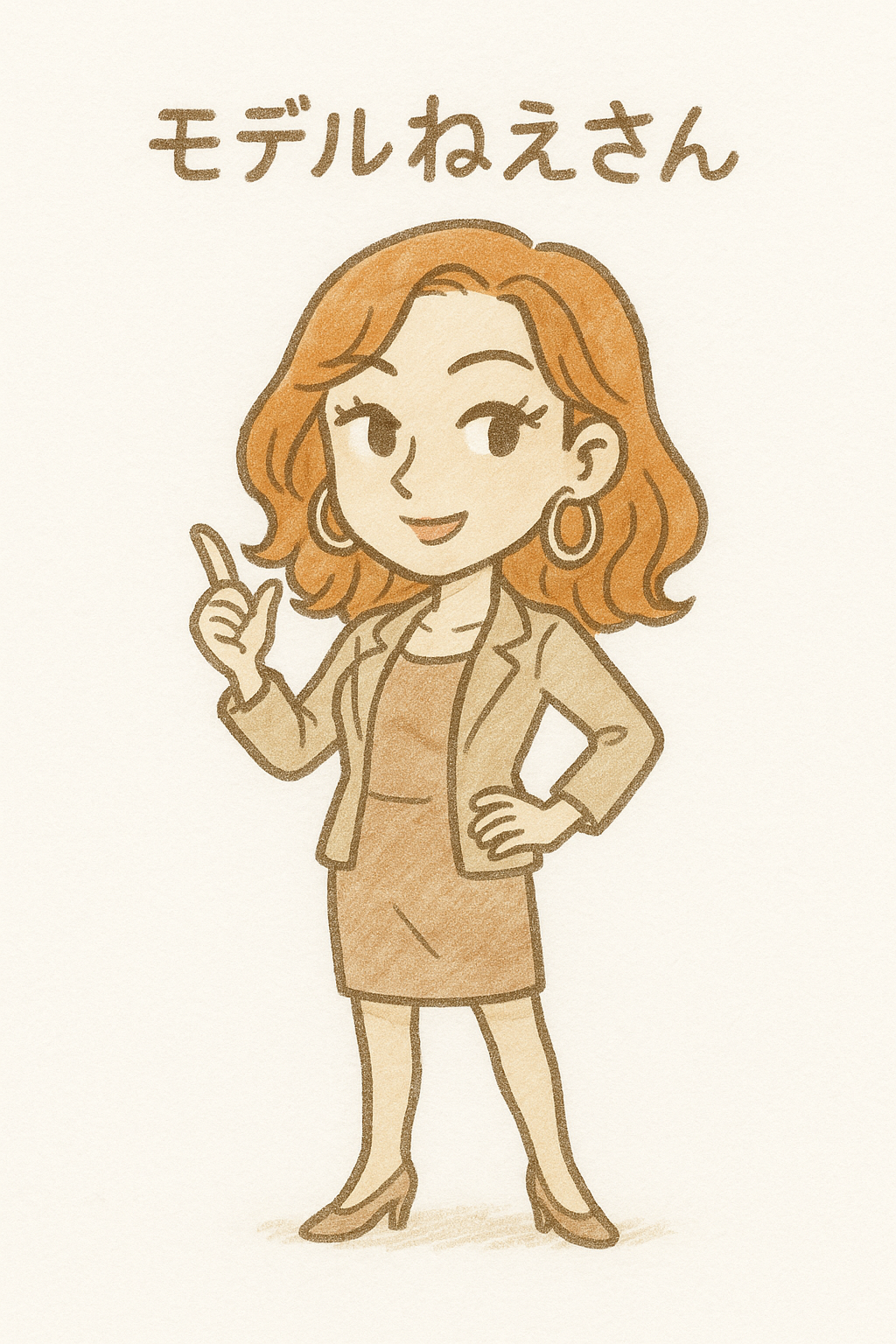
その通り。どんな大学でも、自分が何を学ぶかが重要なの。その大学だからこそ得られる経験や人との出会いもある。みんな、大学は一つの選択肢に過ぎないことを忘れないでね。Tryしてみな?

やっぱり、自分に合った大学選びが鍵だっちゃ。目の前の道をしっかり見つめて、進むべき方向を決めていけばいいんだね。

可能性、盛りだくさんかも!迷ってるより、ちょっとだけ前へっビー!
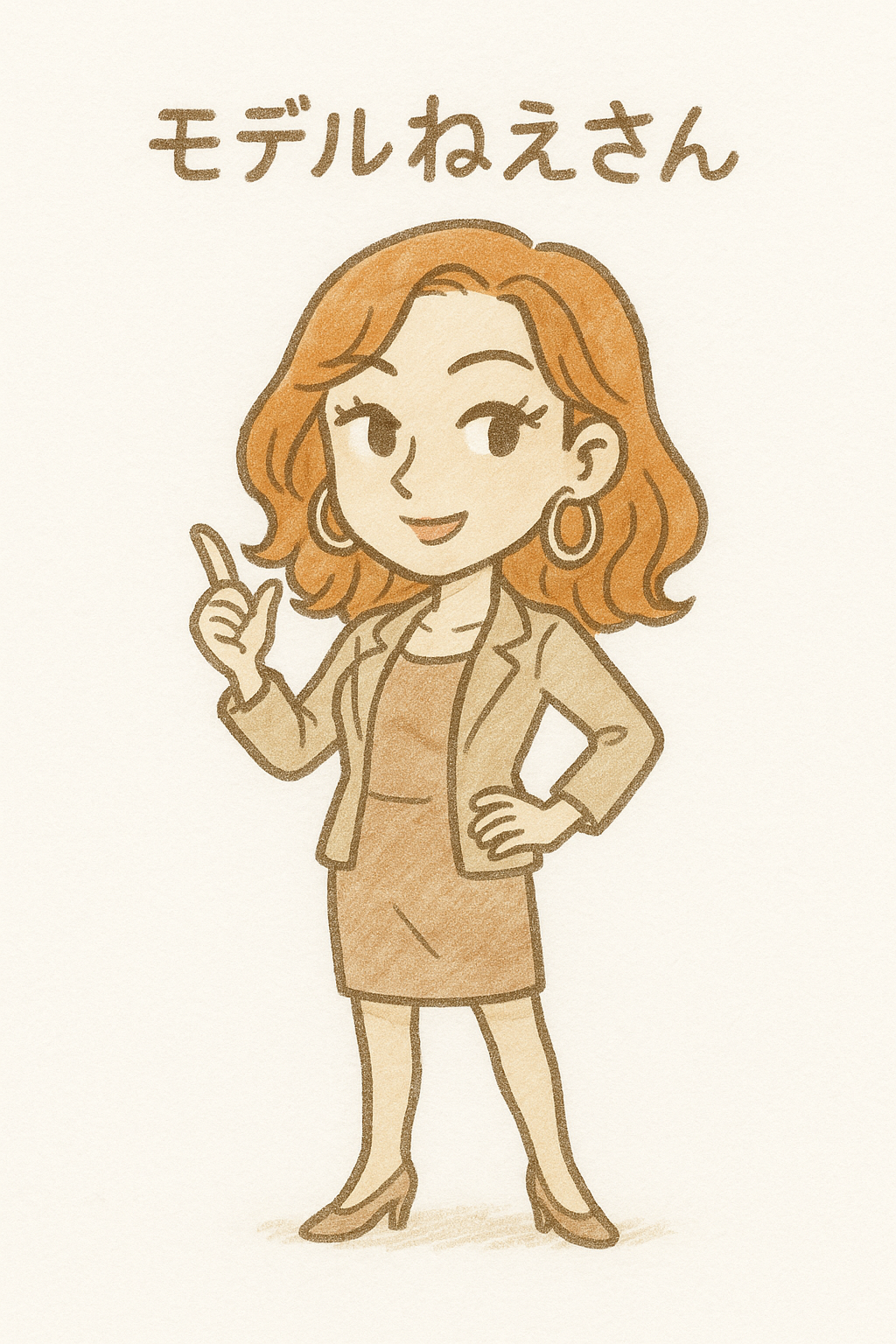
その意気よ!進学の選択肢をシンプルに考え、自分の未来に繋げていくことが大切なの。ふたりも、自分自身の道をしっかりと見つけて進んでいってね!